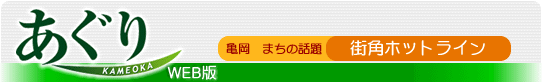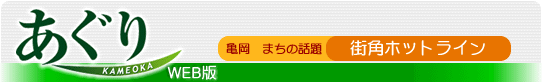| |
[旭地区・藤原翠子情報員]
 旭町印地区では、毎年1月15日は「とんど」の日です。前日にしめ飾りを取りはずし、縁の上手に一まとめにして、家中の神棚とはずしたしめ飾りにお灯明をあげ、ご飯をお供えします。15日の朝には、お灯明と小豆粥をお供えします。 旭町印地区では、毎年1月15日は「とんど」の日です。前日にしめ飾りを取りはずし、縁の上手に一まとめにして、家中の神棚とはずしたしめ飾りにお灯明をあげ、ご飯をお供えします。15日の朝には、お灯明と小豆粥をお供えします。
まず、神主(家の順番制)が薪に火をつけ、1番に氏神様のしめ飾りを燃やしてから、各家から持ち込まれたしめ飾りを燃やし、河川敷の近くでとんどをします。この火に暖まると風邪除けになるといいます。
お餅を2つ焼き、灰と一緒に持ち帰って神棚にお供えし、残りを家族で分け合っていただきます。お餅は病魔除け、灰は家の周りにまき、火難除けにとのことです。
また、青竹1本を火の中に入れて油抜きします。家族の中に妊婦がいると、大きな音で弾けたら男の子、小さい時は女の子が生まれる等と冗談が飛び交います。戸主たちは竹を持ち帰り、お箸を作って神棚にお供えし、残りは菜箸などにして使います。
素朴な行事が絡んでいて、忙しい中にもほのぼのとした心温まる暮らしをする、という伝統があるそうです。
|
|