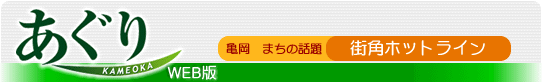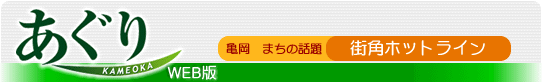| |
[大井地区・山本勇情報員、光嶋幸子情報員合同取材]
大井町南金岐では、どんど焼きを1月12日の日曜日に繰り上げて区内1か所に集中して行い、燃えさかる炎に今年の年占いをしました。
正月のしめ飾りや去年のお札やお守りを炎の中に収め、感謝と今年の幸せを祈りました。青竹を炎の中に入れ、頃合いを見て爆竹の如く音響高く鳴り響かせ、今年の盛運を占いました。その竹を細かく割って家に持ち帰り、神仏と出入口に立てかけるとともに、しめ縄を燃やした灰を家の周囲にふりまき疫病除けの行事としています。どんどの火で餅を焼き、無病息災の祈りを込めて家族みんなでいただきます。
私たちの子供の頃から、こうした風習が親から子に教えられ、今また私たちから子供や孫に教えて、古き良き風習を地域の文化として伝承したいと、今年も区民参加で盛大に行いました。 |
|